COLUMN
- フィレオ・フィッシュの小骨
- 日常のサハンジ
- 笛を吹いてアルコール
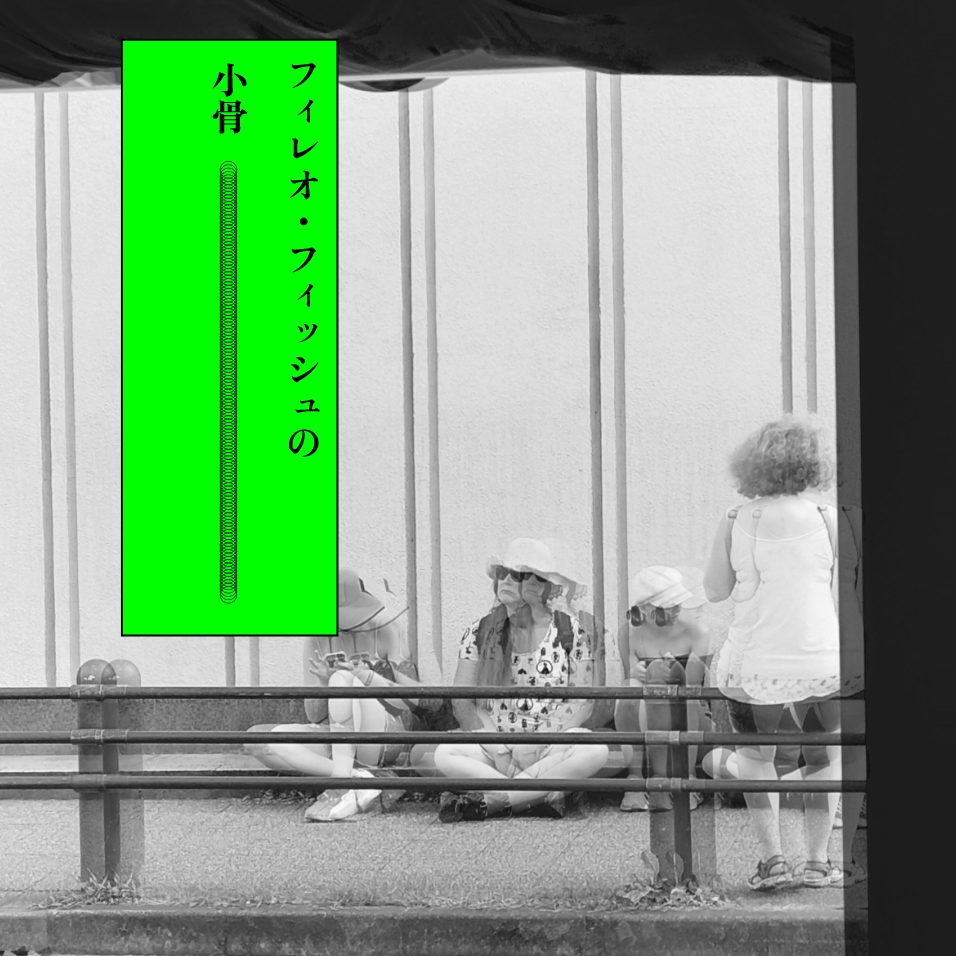
フィレオ・フィッシュの小骨
『UPTO IMAGE LOOK 2023の場合』
2025年に突入してからというもの、ビジュアル制作のことばかり考えている気がする。思えば、年明け一発目の(しっかり目の)仕事も1月10日に三浦半島で敢行したKINLOCH ANDERSONのルック撮影だった。2024年は洋服を作って販売したり、出張に出かけたり、本を出版したり、そんなことばかりやっていたから(自分が携わっているプロダクトのイメージルック以外には)ビジュアル制作をほとんどやってこなかった気がする。しかし、縁とは不思議なもので、2024年中に(抱えきれずに)手放した仕事が幾つかあったと思ったら、なぜか今度は他社の方からビジュアル制作の仕事を立て続けに頂くことになった。そういうわけで、2025年上半期の僕は脳内CPUの一部をそれなりのボリュームで「ビジュアル制作」に対して割いている感じになっている。当たり前のことだが、他人のブランドには他人のストーリーがあるので、ビジュアル制作の過程ではイタコのように「他人のストーリー」を自ら(NEJI)に憑依させる必要がある。なんというか、ただ単純に「カッコいい」とか「洒落てる」とか「今っぽい」とか「俺の世界線」とか、それだけじゃダメな気がするのだ。
そう言った意味で、僕がこれまでに手がけてきたビジュアル制作において、とても印象的だったのは2023年に撮影したファッションブランド「UPTO(ウプト)」のイメージルックだった。同ブランドのデザイナー・山下厚子さんは僕の前職時代の同僚で、(2000年の同期入社という縁も手伝って)もはや25年以上の付き合いということになる。メンズの僕から見ても、彼女のアグレッシブ(勿論、洋服の基礎はバッチリと見に付いている)かつ大胆な着こなしは超絶・洒落ていて、僕が知る女性の中でお洒落度ランキングを付けると確実にトップ5に入る人で、古着もハイブランドもメンズアイテムも難なく着こなす名人だ。しかし、アグレッシブな着こなしの一方では凄く繊細な部分を持ち合わせているというか、写真や詩が好きだったり、世界観は意外(失礼?)に乙女っぽかったりして、まぁ何と言うか一筋縄ではいかない。そんな「UPTO」のイメージルックを作ることになった僕は、とりあえず山下さんに「断片的でもいいから、自分の(UPTOにかける)思いみたいなものを提出してほしい」と頼んだ。案の定、彼女からはもはや散文とも言えないような不器用な言葉のかけらが断片的に届いた。しかし、この思念の散らかりを一束にまとめて視覚化するのが僕の仕事。まず、僕は(山下さんのイメージのかけらを集めて)一篇の現代詩を書くことにした。そして、UPTO IMAGE LOOK 2023。
「UPTO」のアイテムにはユニセックスを謳っているものもあるが、今回のお題は女性向けのサロペットパンツだったため、とりあえず女性モデルを探せばよい。しかし、僕が書いた詩の中から立ち昇ってきたのは「あなた」と「わたし」の世界。主人公の女性モデルとは別で「あなた」の存在をどうしても写しておきたいと思った。この場合の「あなた」は主人公の「わたし」に言霊を与えに来るような存在、つまり、いつも「わたし」を見守ってくれてはいるんだけど(実在するんだかどうだか分からない)精霊のような人が良いと思えた。色々と思案を巡らせた結果、主人公の女性モデルには本保慶ちゃん。彼女とは共通の知人を介して知り合ったが、本業は写真家だ。そして、言霊を携えた「あなた」役には、以前に僕と共同執筆で本を作ったことのある島口大樹くんを据えた。彼は若干23歳で芥川賞候補にまで選出された気鋭の小説家だ。そして、要のフォトグラファーには伊藤君。普段の彼は企業に勤めているサラリーマンで(以前から彼が撮る写真の素晴らしさは知っていたけれど)、仕事として依頼を受けてフォトグラファーを務めたことは一度もない、という。つまり、この撮影は「監督/スタイリストが詩を書き」「写真家と小説家がモデルを務め」「サラリーマンが写真を撮る」という、全員が通常状態を半回転させたような不安定布陣となったわけである。自分でキャスティングを組んでおいてナンだが、我ながらスリル満点である。伊藤君と打ち合わせた結果、まだ朝霧が立ち込めるような時間帯の箱根・芦ノ湖をロケ地に決定した。撮影当日、伊藤君は車で僕の最寄り駅前まで迎えに来てくれた。AM2:40だった。
慶ちゃんにはホワイトとネイビーのサロペットパンツで2コーディネートを組んだ。ホワイトの方には白いターバンを合わせ、思念の渦の中を漂流する旅人のようなイメージで。ネイビーの方には、シンプルな白いシャツと1930年代のフランス製レザーサンダルを合わせ、少しだけ少年っぽく。女性の中にある揺らぎとか二面性みたいなものを壊れそうなタッチで表現した。また、島口君は時空を超えて「わたし」に言葉を届けに来る伝達者の役なので、同じく1930年代のフランス製ジレと1900年代のアンティークロングシャツを合わせてオールホワイトのルックに。足元は裸足。空気に溶けてしまいそうな姿。彼の存在はもしかすると「わたし」以外には見えないのかもしれない。二人を乗せたボートを追う形で、僕と伊藤君も湖へと漕ぎ出す。慶ちゃんは撮り方を知っているから、写り方も知っている。島口君は言葉の伝え方を知っている(ここでは小説家ではなく)伝達者だ。ボートを操縦する僕とアングルの相談をしながら伊藤君はフィルムカメラのシャッターを惜しげもなく何百回も切り続ける。慶ちゃんが肩にかけているストールが風に靡く。朝霧が煙る湖の上で2023年という同時代性は消失し、そこには只いつかの「あなた」と「わたし」だけが在った。およそ5時間にも及ぶ追走劇を終えてボートはようやく船着き場へと戻り、伊藤君はカメラを置き、島口君と慶ちゃんは着替えに行った。僕は衣装をまとめながら、いま初めて現在に戻ってきたような感覚になった。湖のほとりにある食事処へ入り、みんなでカレーを食べてコーヒーを飲んだ。なんだか夢でも見ていたかのような時間だったが、後日、伊藤君から届いた写真を見たら、やっぱりそこには時間が止まった「永遠」が写っていた。湖の幽玄、こだまする言葉、愛と追憶の物語。UPTO IMAGE LOOK 2023。
2025.04.01
